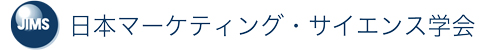2025年度プロジェクト研究
市場に関する研究部会
代表者
関西学院大学 西本章宏
研究計画概要
消費者行動研究において、カテゴリー研究は、認知心理学的研究を基礎とした主たる研究分野の一つである。マーケティング・サイエンスにおいて、競争市場構造分析は、計量的アプローチを基礎 とした主たる研究分野の一つである。本プロジェクトではこれらの融合を試みる。
マーケティング方法論と実務応用に関する研究部会
代表者
慶應義塾大学 星野崇宏
研究計画概要
マーケティング・サイエンスの基礎研究としての計量経済学・統計学・機械学習・行動経済学・産魚組織論の研究とマーケティング応用を行う。可能な限り実務に応用し企業意思決定にも有用な知見を得ることを目的に、部会においては実務家にも発表を行っていただく機会を設けたい。
東アジアの消費者行動とマーケティング戦略研究部会
代表者
一橋大学 上原渉
研究計画概要
日本企業のアジア進出のみならず、中国・アジア企業のマーケティング活動や、日本を含むアジアの消費者行動研究、特に観光関連の消費について議論する。2~3か 月に 1 回程度で研究会を行う予定である。
分析的マーケティング研究部会
代表者
明治大学 水野誠
研究計画概要
1. 定期的に相互の研究成果を報告するとともに研究の最新動向について情報・意見交換を行なう。
2. マーケティング・サイエンスの枠に捉われず,幅広く隣接分野の研究者と交流する機会を得る。
3.以上に基づく研究成果を学会で発表するとともに,学会誌へ投稿を目指す。
消費者・市場反応の科学的研究部会
代表者
東京大学 阿部誠
研究計画概要
企業から実際のデータ、特にCRMやOne-to-One Marketingに有用な個人のトランズアクション・データを含んだもの、を使って、それをメンバーの有志が分析、発表し、ディスカッションする予定である。
データとしては、百貨店のFSPデータ、消費者金融系の利用履歴データ、Eコマースサイトのログファイルなどを想定している。
ID-POSデータのマーケティング活用研究部会
代表者
千葉大学 佐藤栄作
研究計画概要
データ解析コンペティション合同部会(中間報告会・最終報告会)の開催・運営、ならびにID-POS等データのマーケティング活用のための手法等研究を実施する予定です。
学実ブリッジ部会フェーズ5
代表者
共立女子大学 野沢誠治
研究計画概要
本部会では、実務の視点や課題を基にしながら、「B2Bマーケティングの体系化」と「企業ブランドの構築」という研究テーマを取り扱う。マーケティングのサイエンス化はB2C領域が中心であり、B2B領域は、勘と度胸で動いていたが近年、実務ではMA(マーケティング・オートメーション)等のアプリの普及と共にデータに基づく活動が普及しつつある。そこで、急速に変化しているB2Bマーケティングの体系化を試みる。一方で、多くの企業がSDGs等の社会貢献の取組を通じ企業価値(企業ブランド)を高めていこうという動きは、B2CだけでなくB2B企業でもみられる。そこで、「B2Bマーケティングの体系化」と「企業ブランドの構築」の2つを並行して進めると同時に、メンバー各位の問題意識も随時取上げ、研究を進めて行く。
マーケティングにおけるイノベーションとコミュニケーションの研究部会
代表者
慶應義塾大学 濱岡豊
研究計画概要
http://news.fbc.keio.ac.jp/~hamaoka/cgi-bin/fswiki/wiki.cgi?page=JIMS
マーケティングにおけるイノベーションからコミュニケーションに渡る幅広い範囲のトピックを扱う。
2025年度は(1)製品開発に関する継続調査の実施、(2)ユーザー・イノベーションの規定要因の解明、(3)事例ベース意思決定モデルの応用研究、(4)放射線疫学データ分析や新型コロナウイルス流行へのマーケティング・サイエンス手法の適用を中心に理論的、実証的研究を行う。大学院授業と連動することによって、修士、博士論文の作成も指導する。
消費者行動とマーケティング意思決定の研究部会
代表者
慶應義塾大学 里村卓也
研究計画概要
消費者行動とマーケティング意思決定をとりまく環境は大きく急速に変化している。消費者間相互作用や企業と消費者による価値共創、グローバル環境下での市場競争、新しい技術のマーケティングへの導入等々、これらの環境変化は消費者行動とマーケティング意思決定に大きな影響を与えている。本プロジェクトでは、このような新しい環境下での消費者行動とマーケティング意思決定に適応できる、新しいアイデアやコンセプト、手法について探求する。
部会HP(会員からのPJに関する問い合わせ等):https://www.fbc.keio.ac.jp/~satomura/jims_pj
コンテンツとコミュニケーション研究部会
代表者
大妻女子大学 野澤智行
研究計画概要
マーケティング分野におけるコンテンツとコミュニケーションに関心を寄せる学識者と実務家が参加し、研究報告とディスカッションを行う月例部会を、電通本社およびオンラインにて開催する。2024年度は「野生の統率 アニメ制作におけるクリエイションとプロデュースの発現」、「広告エンドーサーとしてのVTuberの効果 -YouTuberとの比較-」、「神奈川産学チャレンジプログラム中間報告」、「デジタルシフト時代におけるユーザー接点チャネルの仮説検証」、「株を通して社会を学ぶ ー新NISA時代の教育実践ー」、「福井市の観光政策 ~北陸新幹線福井開業に向けての観光PRとは~」などをテーマに取り上げた。2025年度も最新トレンドの捕捉を念頭に、SNSを日常的に用いるZ世代も招き、実証研究およびモデル構築を進展させる。
マーケティングの統計的モデリング研究部会
代表者
筑波大学 伴正隆
研究計画概要
統計学との古い関わり方をはるかに超えて,多変量解析や時系列モデルの応用,MCMCを用いたベイズ統計分析,さらに機械学習も盛んに行われている。これら大規模データをマネジメントのために解析する統計手法の開発と応用について研究し,最新の統計的モデリング手法を適用した新しいマーケティングモデルの開発と,実際の問題への応用を研究目的とする。
ブランドマネジメント研究部会
代表者
法政大学 豊田裕貴
研究計画概要
ブランド・マネジメントに関する理論的、実務的研究を、メンバー各自のテーマに応用する。その際、定量分析のみではなく、定性分析も併用する混合研究からのアプローチも試みる。
社会問題とコミュニケーション研究部会
代表者
筑波大学 西尾チヅル
研究計画概要
SDGsや地球環境問題、高齢化社会等のグローバルな社会課題、IoTやICT等の高度情報通信技術の進歩、ソーシャルメディアの台頭等のさまざまな社会課題と消費者行動との関係を、マーケティング・サイエンスの観点から多面的に分析し、それらの領域におけるマーケティング・コミュニケーションの役割と課題を明らかにする。
消費者行動の学際的研究部会
代表者
早稲田大学 守口剛
研究計画概要
消費者行動研究は近年大きく進展してきている。その原動力の一つは、学際的な研究の活発化である。もともと消費者行動研究は学際的な色彩が強い領域であったが、近年ではその性質がより色濃くなってきている。本研究会では学際的なアプローチによって、消費者行動に関する多面的な研究を行う。
Webコミュニケーション・データのマーケティング活用研究部会
代表者
横浜国立大学 鶴見裕之
研究計画概要
家計簿アプリデータ、シングルソースデータ等のデジタル・マーケティング・データを、より効率的、効果的にマーケティングに活用する手法を研究会のメンバーとの議論を重ね検討する。
3ヶ月に1回程度、部会を開催し、ゲストスピーカーなどを交えつつ、研究報告や意見交換を実施する。
市場予測のための消費者行動分析研究部会
代表者
大阪公立大学 中山雄司
研究計画概要
本研究部会では消費者の行動をマーケティング・サイエンス、消費者行動研究、社会学などのさまざまな視点から研究し、市場予測に寄与することを目的とする。具体的には、購買者行動の確率モデルの理論研究、参照点形成に関する既存研究のレビュー、それに続く理論・実証研究、データ解析コンペティション関西予選運営などを行う予定である。
顧客データからの深い知見発見プロジェクト研究部会
代表者
明治学院大学 斉藤嘉一
研究計画概要
本年度の計画は以下の2点である。一つは,過去の大会で発表した研究成果を論文として仕上げていくことである。JIMS112で発表した「加齢が健康訴求商品の購入に与える影響」,JIMS113の「陳列SKU数とクチコミの関係」,JIMS114の「オンライン無料プレゼントキャンペーンはオフライン購買を促進するか?」を2025年度に投稿することを目指し,追加分析を行うなど研究を改善していく。もう一つは,新たな研究への取り組みである。小売店頭での買い物客の視線と脳波を測定し,このデータを用いて小売店頭における購買意思決定プロセスを探っていく。また部会では,部会メンバー,及び必要に応じて学会員以外の研究者に研究発表をしてもらい,これについて議論することで,各メンバーの研究の質を高め,将来の研究に向けて視野を広げる。
マーケティングのデータ分析とモデリング・アプローチ研究部会
代表者
大阪大学 ウィラワン ドニ ダハナ
研究計画概要
研究参加者が抱いているマーケティングに関する諸問題について幅広く取り上げ、その問題をあつかうためのモデル化に取り組み,データに基づいた実証分析を行う。また学術雑誌などを参照し、現在注目されている研究課題についてもフォローしていきたいと考えている。